1次試験の勉強方法
私が試験までにしたことを10ステップでご紹介します。
私がやっていた勉強法は、読むことをメインとした勉強方法です。
書いたり、自分の言葉でノートにまとめたりしたほうが覚えられるという方もいらっしゃると思いますが、
とにかく勉強が嫌いだった私にとっては、机に座る、ノートを開く、読んだ文章を自分の言葉で考える、書く、
という行動がすべて「勉強面倒くさい」に繋がってしまいました。おまけに時間をかけて覚えたつもりの内容も忘れてしまうとさらに勉強から遠のきたくなります。
ですので私は、『他の行動から勉強に切り替えるまでのステップ数を最小限にすること』、「●●を覚える」という目標ではなく『「●ページから△ページまでを読む」
という行動の目標を立てること』、『1つの項目になるべく時間をかけずに何度も繰り返すことで覚えること』を徹底していました。
この方法にしたことによって、スキマ時間にスマホよりも教科書に手が伸びるようになり、「あー勉強しないと」と腰が重くなったり、勉強したことを思い出せなくて
「また忘れてる」と落ち込んだりすることもなくなりました。
私が一次試験までにしたことを10ステップに分けて詳しくご紹介します。
contents
もくじ
01
重要箇所を抜粋しているYouTubeを聞き流す
色彩検定2級の受験時もそうでしたが、私の受験勉強を始めるときのモチベ―ジョンは「受験までに7回読めたらいいな」という感じです。これだけ聞くと「7回も読めない…」と思われるかもしれませんが、1回1回全ての文章を理解して読むというよりはサラサラと流し見しているようなイメージです。
本当は初めから教科書を読み進められたらいいですが、私の場合初めて見る文章はどうしても拒絶反応が出てしまうので、まずは教科書の内容を数時間程度にまとめてくれている動画を聞き流していました。
このステップを踏むことで、初めて教科書を読むときも「動画でこんなこと言ってたな」と思うことが数回はあります。たった数回でも、初めから教科書を読んで「こんなの覚えられないよ…」と絶望する気持ちが少しは緩和できます。
本当は初めから教科書を読み進められたらいいですが、私の場合初めて見る文章はどうしても拒絶反応が出てしまうので、まずは教科書の内容を数時間程度にまとめてくれている動画を聞き流していました。
このステップを踏むことで、初めて教科書を読むときも「動画でこんなこと言ってたな」と思うことが数回はあります。たった数回でも、初めから教科書を読んで「こんなの覚えられないよ…」と絶望する気持ちが少しは緩和できます。
02
YouTubeで抜粋されている箇所を蛍光ペンでマーク
教科書を開き、動画を流しながら動画で抜粋されている箇所を蛍光ペンでマークします。このステップによって教科書の文字の羅列に強弱が生まれて読みやすくなります。

03
レイアウトを感じつつ斜め読み
いよいよ動画無しで教科書を読み始めます。まずは章名、節名、項名に注目して読み進めます。文章を読む前にまずはその文章が何についての説明なのかを事前に把握していきましょう。文章自体は流し読み程度で読み進めてください。
このやり方で1週間に3周読むことを目標とします。読み方は初めから最後までを3周してもいいですが、私は1周サラサラと読んでから2周目と3周目は章ごとに2周ずつ読んでいました。
ここではとにかく1週間ということにこだわりたいです。短期間でしんどいと思いますが、私はモチベ―ションをあげるために章ごとに正の字を書いて数えていました。
1週間で正の字を「3」にできるように頑張りましょう!
このやり方で1週間に3周読むことを目標とします。読み方は初めから最後までを3周してもいいですが、私は1周サラサラと読んでから2周目と3周目は章ごとに2周ずつ読んでいました。
ここではとにかく1週間ということにこだわりたいです。短期間でしんどいと思いますが、私はモチベ―ションをあげるために章ごとに正の字を書いて数えていました。
1週間で正の字を「3」にできるように頑張りましょう!
04
頻出する用語や詳しく説明されている用語を意識する
4周目からは文章内の用語に注目します。用語を覚えようとするよりは「ここに用語がある」「この用語の説明文はここまである」というようにレイアウトを把握するようなイメージです。
出来たら正の字「4」です。
出来たら正の字「4」です。
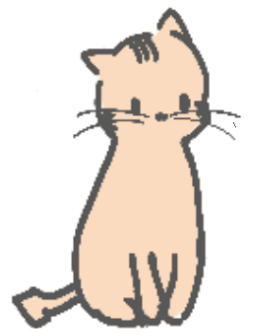
05
用語と用語の間の説明文を意識する
「04」で注目した用語の説明文を意識して読み進めます。とにかく「覚えよう」と自分に圧をかけずサラサラ読みましょう。
出来たら正の字1つ完成です。
出来たら正の字1つ完成です。
06
点数より問題慣れ重視で過去問を解いてみる
このタイミングで過去問を2年分解いてみましょう。点数は気にしなくて大丈夫です。私はこの時点で4割くらいしかとれませんでした。
あくまでどんな問題形式か把握することが目的です。
ここで注意していただきたいのが、「2021年以降の過去問をする」ということです。2019年以前は改訂前の範囲となっており、2020年はコロナで試験が中止されていて過去問がないので、必ず2021年以降の過去問を解いてください。
あくまでどんな問題形式か把握することが目的です。
ここで注意していただきたいのが、「2021年以降の過去問をする」ということです。2019年以前は改訂前の範囲となっており、2020年はコロナで試験が中止されていて過去問がないので、必ず2021年以降の過去問を解いてください。

07
表や図を問題目線で見たり、現象や効果をイメージする
6周目になると図にも注目できる余裕が出てきます。特にxy色度はそのまま出題されることもあるので色の場所を覚えておくと良いと思います。
私は図や式を理解することが本当に苦手で、初めは等色相三角形やNCSの有彩色の表示方法など数字やアルファベットが沢山出てくると拒否反応が出て全く理解できませんでしたが、5周目までの知識で理解できるようになっていました。
今までサラサラと読んでいましたが、ここからは今までの勉強を信じて文章からイメージを膨らませながら読みましょう。
出来たら正の字「6」です!
私は図や式を理解することが本当に苦手で、初めは等色相三角形やNCSの有彩色の表示方法など数字やアルファベットが沢山出てくると拒否反応が出て全く理解できませんでしたが、5周目までの知識で理解できるようになっていました。
今までサラサラと読んでいましたが、ここからは今までの勉強を信じて文章からイメージを膨らませながら読みましょう。
出来たら正の字「6」です!
08
書かれていることを予測しながら読む
7周目になると教科書のレイアウトや次に何の説明があるということを把握している状態になります。「次はこの説明が始まるな」と予想しながら読み進めましょう。
出来たら正の字「7」!目標達成です!!
出来たら正の字「7」!目標達成です!!

09
苦手な章を+3周読む
試験日までは苦手な章を+3周読みましょう。
私は苦手な「測色」と「色彩心理」の章に加えて、毎年出題されている「景観色彩」の章を+3周読みました。
私は苦手な「測色」と「色彩心理」の章に加えて、毎年出題されている「景観色彩」の章を+3周読みました。
10
残りの過去問を解く
「09」と並行で「06」で解かなかった過去問を解いておきましょう。

